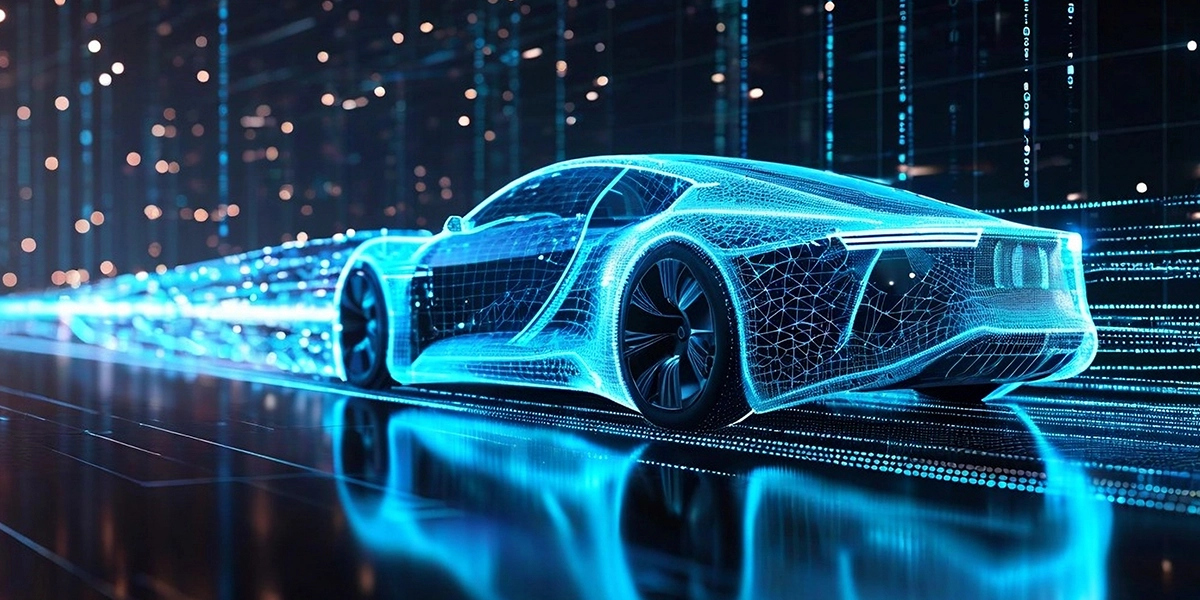SDV(Software-Defined Vehicle)への移行に伴い、世界の自動車産業は大規模な変革期を迎えている。差別化戦略から車両の設計や製造に至るまで、バリューチェーンのどの側面もこの移行に手付かずのままです。
業界が慣れ親しんできたドメインベースのアーキテクチャからの大きな脱却を意味するという意味で複雑であり、それが解き放つ可能性の大きさゆえにエキサイティングである。
以下の段落では、この進化がボンネットの下で、そして研究開発から製造現場まで、業界の屋根の下でどのように進行しているかを紹介する。
ソフトウェアのDNAはECUの乱雑さと相容れないかつて自動車エレクトロニクスを定義していた伝統的なドメインベースのアーキテクチャーは、時代遅れになりつつある。自動車は歴史的に、ブレーキ用、インフォテインメント用、パワートレイン用など、ドメインごとにECUを重ねることでその能力を高めてきた。現代の自動車は 150近いECUで構成されていると推定されている 。しかし、SDVのパラダイムは根本的に異なるDNAを要求している。アジャイルでスケーラブルであり、継続的な進化のために設計されている。
SDVでは、機能はハードウェアに縛られるのではなく、ソフトウェアに依存します。レガシーECUの乱立は、通信レイテンシを増大させ、ケーブル配線を肥大化させ、製造の複雑性を高める。これは、SDVが必要とするモジュール性とリアルタイム応答性とは相反するものです。その答えは、ゾーンアーキテクチャです。強力な中央プラットフォームに計算を統合し、地域の ゾーンコントローラが ローカライズされたセンサーとアクチュエータのデータを管理します。
ゾーン設計は、ケーブルの重量を劇的に削減し、診断を合理化し、モデルやバリエーション間で電子バックボーンを標準化します。これにより、部品表(BOM)と組み立て時間が短縮されるだけでなく、OEMはバリエーション固有のハードウェアの決定をより生産に近い段階で遅らせることができ、これまでにない柔軟性が実現します。車両のライフサイクル全体にわたって、ゾーン設計は、より迅速なOTAアップデートとモジュール修理を促進し、TCOを削減します。
トリムやモデルイヤー間のハードウェアのばらつきが少ないため、OEMは複数の車両にわたって研究開発を償却することができ、車両全体を再設計することなく、生産サイクルの後半で構成を変更することもできます。
新しいエレクトロニクスとソフトウェアスタックのための配線の変更ゾーナルアーキテクチャは、SDVと互換性のない論理的・物理的ボトルネックの多くを一掃する。この新しい青写真を補完するのが、高性能コンピューター(HPC)、仮想化、階層化された抽象化を中心に構築された新しいエレクトロニクスとソフトウェアのバックボーンである。ECUは、リアルタイムOS(セーフティ・クリティカルなループ用)と汎用OS(非クリティカルなサービスとデータ処理用)をホストするゾーン・ゲートウェイと集中型コンピュート・クラスタに置き換えられる。
通常、仮想化は、ADASの知覚、エンジン・レスポンス、コックピット・インフォテインメントなど、分離されたワークロードを実行するためにCPUとGPUリソースを分割するために活用される。I/O仮想化により、各VMはミリ秒レベルのレイテンシでセンサーやアクチュエーターにほぼネイティブにアクセスできる。ハードウェア抽象化レイヤとミドルウェアは、統一されたAPIを公開するため、開発者はチップごとにデバイスドライバを書き換える代わりに、ポータブルなマイクロサービスを書くことができる。
このスタックは3つの主要な利点を提供する。安全機能の決定論的性能、迅速なOTA機能展開、そして車両ライン全体でソフトウェアを再利用する俊敏性である。これらの反論の余地のない利点により、この新しいスタックは自動車バリューチェーン全体の再編成の引き金となるだろう。OEM、ティア1サプライヤー、シリコンベンダーは、取引当事者から共同イノベーション・パートナーへと進化する。この協力的なエコシステムでは、ハードウェアメーカーは性能と安全性の認証に注力し、OEMとソフトウェアメーカーは継続的に機能を反復する。
サービスの推進:新しいデジタル・モビリティ・エンジンとしてのSOAサービス指向アーキテクチャ(SOA)は、ゾーン型SDVの設計と完全に連動しており、インフラ、アプリケーション、プレゼンテーションの関心事をきれいに分離することで、ソフトウェアスタックに秩序をもたらします。SOAの核心は、ルートプランニング、バッテリー管理、音声制御などの各機能を、モノリシックなECUバスではなく、明確に定義されたミドルウェア・チャネルを介して通信する独立したサービスとして扱うことです。
この3層モデルでは、インフラ層がハードウェアの抽象化、仮想化、データルーティングのミドルウェアをホストする。HPCリソースとセキュアなメッセージバスをマーシャルし、各サービスが必要なCPUサイクル、メモリ、センサーフィードを確保する。シリコンごとにドライバを書き換える必要はない。
その上のアプリケーション層では、個別のマイクロサービスが実行される:ADASアルゴリズム、エネルギー最適化ルーチン、OTAアップデート・マネージャー、サードパーティ製アプリなどだ。各サービスは独立してバージョン管理、拡張、ロールバックが可能で、機能展開を加速し、障害を分離する。ここでは、ミドルウェアがリソース割り当て、サービス・ディスカバリー、エンドツーエンドの暗号化を処理するため、セーフティ・クリティカルなループは決定論的であり続け、クリティカルでないサービスはスタートアップのペースで進化する。
最後に、プレゼンテーション・レイヤーが これらのサービスを結束したUXに仕上げる。UIコンポーネントは同じサービスAPIを利用するため、OEMは車両のコアロジックに触れることなく、ダッシュボードを刷新したり、新しいHMIパラダイムを導入したりすることができる。
サービスを利用することで、自動車メーカー、ティア1、ソフトウェア・パートナーは、硬直したサプライ・チェーンから、すべてのサービスが共有ミドルウェアのシャーシにプラグインされる、協力的なプラットフォーム経済へとシフトする。
未来は見た目よりも近い2030年までに、自動車部品に占めるソフトウェアの割合は 10%未満から50%に上昇する 。この急増により、自動車は常に進化し続けるデジタル・プラットフォームと化す。アプリ・マーケットプレイス、機能サブスクリプション、隔週OTAによる機能強化などが考えられる。ハードウェアがコモディティ化するにつれ、OEMは馬力よりもコードの品質で競争するようになるだろう。見かけよりもずっと近いこの現実(投資家はすでに、 SDVへのシフトに取り組んでいる企業に報酬を与えている )において、開発サイクルは数年から数ヶ月に短縮され、ソフトウェア、シリコン、モビリティにわたるグローバルな戦略的パートナーシップが市場のリーダーを定義することになるだろう。